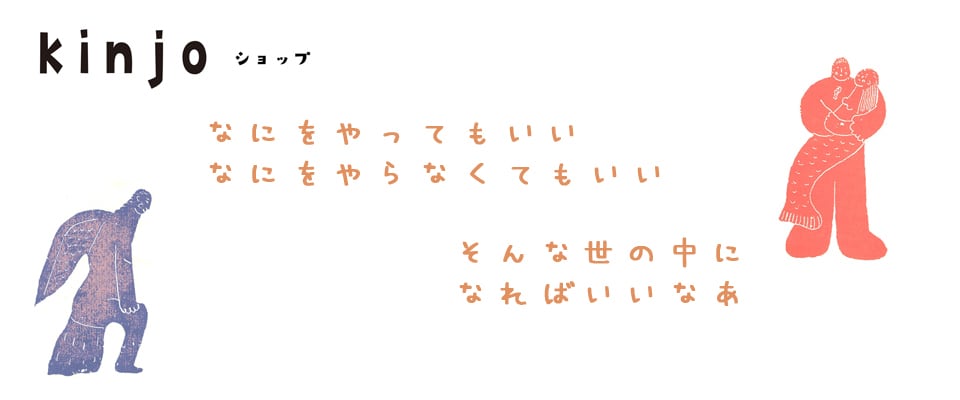-

ラオス 手紬ぎ綿スカーフ 藍グリーンストライプ 倉井由紀子
¥9,900
倉井由紀子さんはタイのチェンマイと名古屋の二拠点で活動する織物作家です。 1年の1/3をタイ、ラオスの地で過ごし、現地の織物を洋服やスカーフに仕立てています。 倉井さんのブランドStudio Bunrinの服は、絹や綿の光沢や手触り、草木染の自然な色合いが印象的で、美しい織柄を生かしたシンプルなデザインが特徴です。 東南アジアの織物を大胆に裁断し、センスのいい洋服などに生まれ変わらせていて、多くのファンがいます。 綿花を育て、収穫し、糸を紡ぐ、あるいは繭を育て繭玉を煮て絹糸を紡ぐ、それを撚(よ)る、その糸を、植物を醸した汁や木の根を煮出した汁で染める。 染めた糸を整えて経糸(たていと)を整経(せいけい)し、機織り機にかける、横糸を通して一段ずつ織る。 糸が出来上がるまでに半年、その糸が民族特有の色鮮やかな織物に仕立てあがるまでに最低1ヶ月、長くて半年かかります。 この、ラオス・サバナケットの手紬ぎ綿スカーフ(縦糸、横糸ともに手紬ぎ糸)は天然発酵藍染めで、藍グリーントライプの織りがとても美しいです。 一年中、お使いいただけます。 長さ 約175cm 幅 約40cm 倉井由紀子さんの仕事 ハセガワトモコ https://kinjonagoya.com/yukiko-kurai-work-2/
-

ラオス 手紬ぎ綿スカーフ トープストライプ 倉井由紀子
¥9,900
倉井由紀子さんはタイのチェンマイと名古屋の二拠点で活動する織物作家です。 1年の1/3をタイ、ラオスの地で過ごし、現地の織物を洋服やスカーフに仕立てています。 倉井さんのブランドStudio Bunrinの服は、絹や綿の光沢や手触り、草木染の自然な色合いが印象的で、美しい織柄を生かしたシンプルなデザインが特徴です。 東南アジアの織物を大胆に裁断し、センスのいい洋服などに生まれ変わらせていて、多くのファンがいます。 綿花を育て、収穫し、糸を紡ぐ、あるいは繭を育て繭玉を煮て絹糸を紡ぐ、それを撚(よ)る、その糸を、植物を醸した汁や木の根を煮出した汁で染める。 染めた糸を整えて経糸(たていと)を整経(せいけい)し、機織り機にかける、横糸を通して一段ずつ織る。 糸が出来上がるまでに半年、その糸が民族特有の色鮮やかな織物に仕立てあがるまでに最低1ヶ月、長くて半年かかります。 この、ラオス・サバナケットの手紬ぎ綿スカーフ(縦糸、横糸ともに手紬ぎ糸)は天然発酵藍染めで、トープストライプの織りがとても美しいです。 一年中、お使いいただけます。 長さ 約175cm 幅 約40cm 倉井由紀子さんの仕事 ハセガワトモコ https://kinjonagoya.com/yukiko-kurai-work-2/
-

ラオス 手紬ぎ綿スカーフ 藍ストライプ 倉井由紀子
¥9,900
倉井由紀子さんはタイのチェンマイと名古屋の二拠点で活動する織物作家です。 1年の1/3をタイ、ラオスの地で過ごし、現地の織物を洋服やスカーフに仕立てています。 倉井さんのブランドStudio Bunrinの服は、絹や綿の光沢や手触り、草木染の自然な色合いが印象的で、美しい織柄を生かしたシンプルなデザインが特徴です。 東南アジアの織物を大胆に裁断し、センスのいい洋服などに生まれ変わらせていて、多くのファンがいます。 綿花を育て、収穫し、糸を紡ぐ、あるいは繭を育て繭玉を煮て絹糸を紡ぐ、それを撚(よ)る、その糸を、植物を醸した汁や木の根を煮出した汁で染める。 染めた糸を整えて経糸(たていと)を整経(せいけい)し、機織り機にかける、横糸を通して一段ずつ織る。 糸が出来上がるまでに半年、その糸が民族特有の色鮮やかな織物に仕立てあがるまでに最低1ヶ月、長くて半年かかります。 この、ラオスの手紬ぎ綿スカーフ(縦糸、横糸ともに手紬ぎ糸)は天然発酵藍染めで、藍ストライプの織りがとても美しいです。 一年中、お使いいただけます。 長さ 約175cm 幅 約40cm 倉井由紀子さんの仕事 ハセガワトモコ https://kinjonagoya.com/yukiko-kurai-work-2/
-

五寸(15cm)のお皿 五枚セット 大蔵真
¥16,500
名古屋の大蔵製盆の木地師である大蔵真(まこと)さんが、ろくろでつくったお皿の5枚セットです。 大きさは、五寸(直径15cm) 高さは2cmくらいです。 材質は、北海道産の栓(せん)という木です。美しい杢目が特長です。 杢目は、木目とは違って特殊な表情が現れたものを言います。 表面は「拭き漆(ふきうるし)」です。「漆塗り」と違って、木目を 生かして仕上げる技法です。 使い込むごと、時間の経過するほどに、漆が透けて、が浮き出てきます。 ◆ 杢目は一つひとつ違うので同じものはありません。ご了承ください。 最後の木地師 大蔵真 https://kinjonagoya.com/%e6%9c%80%e5%be%8c%e3%81%ae%e6%9c%a8%e5%9c%b0%e5%b8%ab/
-

斜め線のカップ 島村直美
¥1,870
優しい斜めの線の模様が刻印されている島村直美さんのカップです。 少しざらついた土に透明釉が施されています。 直径 7~8cm 高さ 8~8.5cm このカップには、口の当たる部分とか高台などに 普段の暮らしの中で使いやすいような工夫が施されています。 作家の島村直美さんは、あまり気どらず、日常の中で使うことを想定してつくっているようです。 日常で輝く器は、意外に少ないはずです。 島村直美さんの器は、毎日の食卓に自然に溶け込み、使い続けることでその存在感を増していき、毎日使いながら、気づかないうちに、なんとなくその日常が豊かになっていくような、そんふうに感じる不思議な魅力があります。 丁寧に暮らしたいな。 自然に、そんな気持ちになってくる器です。 電子レンジは温める程度であれば使用可能です。 食洗器は避けてください。 立ち止まったままから「再開」へ 中村未生さん 直美さん https://kinjonagoya.com/standstill-to-restarting-2/
-

線のカップ 島村直美
¥1,870
優しい線の模様が刻印されている島村直美さんのカップです。 土に鉄分を混ぜて色をつけて、透明釉をかけて焼成しています。 直径 7~8cm 高さ 8~8.5cm このカップには、口の当たる部分とか高台などに 普段の暮らしの中で使いやすいような工夫が施されています。 作家の島村直美さんは、あまり気どらず、日常の中で使うことを想定してつくっているようです。 日常で輝く器は、意外に少ないはずです。 島村直美さんの器は、毎日の食卓に自然に溶け込み、使い続けることでその存在感を増していき、毎日使いながら、気づかないうちに、なんとなくその日常が豊かになっていくような、そんふうに感じる不思議な魅力があります。 丁寧に暮らしたいな。 自然に、そんな気持ちになってくる器です。 電子レンジは温める程度であれば使用可能です。 食洗器は避けてください。 立ち止まったままから「再開」へ 中村未生さん 直美さん https://kinjonagoya.com/standstill-to-restarting-2/
-

線のカップ 島村直美
¥1,870
SOLD OUT
優しい線の模様が刻印されている島村直美さんのカップです。 少しざらついた土に透明釉が施されています。 直径 7~8cm 高さ 8~8.5cm このカップには、口の当たる部分とか高台などに 普段の暮らしの中で使いやすいような工夫が施されています。 作家の島村直美さんは、あまり気どらず、日常の中で使うことを想定してつくっているようです。 日常で輝く器は、意外に少ないはずです。 島村直美さんの器は、毎日の食卓に自然に溶け込み、使い続けることでその存在感を増していき、毎日使いながら、気づかないうちに、なんとなくその日常が豊かになっていくような、そんふうに感じる不思議な魅力があります。 丁寧に暮らしたいな。 自然に、そんな気持ちになってくる器です。 電子レンジは温める程度であれば使用可能です。 食洗器は避けてください。 立ち止まったままから「再開」へ 中村未生さん 直美さん https://kinjonagoya.com/standstill-to-restarting-2/
-

線の皿 島村直美
¥2,530
優しい線の模様が刻印されている島村直美さんのお皿です。 少しざらついた土に透明釉が施されています。 直径 18cm 高さ 2~3cm このカップには、口の当たる部分とか高台などに 普段の暮らしの中で使いやすいような工夫が施されています。 作家の島村直美さんは、あまり気どらず、日常の中で使うことを想定してつくっているようです。 日常で輝く器は、意外に少ないはずです。 島村直美さんの器は、毎日の食卓に自然に溶け込み、使い続けることでその存在感を増していき、毎日使いながら、気づかないうちに、なんとなくその日常が豊かになっていくような、そんふうに感じる不思議な魅力があります。 丁寧に暮らしたいな。 自然に、そんな気持ちになってくる器です。 電子レンジは温める程度であれば使用可能です。 食洗器は避けてください。 立ち止まったままから「再開」へ 中村未生さん 直美さん https://kinjonagoya.com/standstill-to-restarting-2/
-

銀彩のお皿 徳田吉美
¥6,050
徳田吉美さんの美しい銀彩のお皿です。 たて 27cm よこ 19cm 徳田さんの器は、漆蒔とともに銀彩が効果的に使われています。 一般的な上絵付の絵の具よりも少し低い温度で焼成します。 このお皿には銀彩だけで、漆蒔の絵付けは施されていませんが、 シンプルで本当に美しいお皿です。 ペースト状にした銀を塗って焼成したもので、 銀製品と同様で経年変化により色が変色する場合がありますが、 その変化を楽しむことも出来ます。 輝きを取り戻すには、重曹を水に溶いた重曹ペーストを付けて磨いても効果があります。 ※ 電子レンジ、食洗器は避けてください。 漆蒔を継承する現代作家 徳田吉美 https://kinjonagoya.com/%e6%bc%86%e8%92%94%e3%82%92%e7%b6%99%e6%89%bf%e3%81%99%e3%82%8b%e7%8f%be%e4%bb%a3%e4%bd%9c%e5%ae%b6%e3%80%80%e5%be%b3%e7%94%b0%e5%90%89%e7%be%8e/
-

漆蒔のカップ 徳田吉美
¥4,620
徳田吉美さんの漆蒔(うるしまき)と銀彩のカップです。 上直径 7cm 下直径 5cm 高さ 6cm 漆蒔は、陶器の上絵付けの技法の一つです。 陶器の絵付けには、上絵のほかに下絵、イングレーズがありますが、上絵が最も焼成温度が低いため、鮮やかな色彩を表現することができます。 その上絵の中でも、漆蒔は深みのある艶やかな色が出る技法です。 漆蒔は、花を描くというものには適しておらず、一定の面積に均一に絵の具を乗せる技法です。そのため、幾何学的な模様が適していて、陶器の白地に深みのある色彩の線や図形のデザインが、とても美しく映えます。 この徳田さんのカップは、漆蒔の良さが最もよく表現されているものです。 さらに、漆蒔の黄と銀彩のバランスがとてもきれいで、どことなくレトロな雰囲気も魅力です。 漆蒔という技法は、徳田さんの器以外では、ほとんど見かけることはありません。 大倉陶園という有名な食器メーカーが漆蒔の食器をつくっていますが、高価で、数も限られています。 漆蒔の深い色彩を、一度見てほしいです。 〈漆蒔の工程〉 ・上絵付されていない白い陶器の表面に、デザインに合わせて、テレピンでうすめた「漆」をぬります。 ・漆をある程度乾かしてから、上から粉の絵具をまぶします。漆が「のり」となって、絵の具を定着させます。 ・そのあと、800度前後で焼成すると、漆は燃えてなくなり、絵具だけが溶けて完成します。 徳田さんのこのカップの場合は、銀彩のために、もう一度、少し低い温度で焼成する必要があります。 ※ 電子レンジ、食洗器は避けてください。 漆蒔を継承する現代作家 徳田吉美 https://kinjonagoya.com/%e6%bc%86%e8%92%94%e3%82%92%e7%b6%99%e6%89%bf%e3%81%99%e3%82%8b%e7%8f%be%e4%bb%a3%e4%bd%9c%e5%ae%b6%e3%80%80%e5%be%b3%e7%94%b0%e5%90%89%e7%be%8e/
-

漆蒔のカップ 徳田吉美
¥4,620
徳田吉美さんの漆蒔(うるしまき)と銀彩のカップです。 上直径 7cm 下直径 5cm 高さ 6cm 漆蒔は、陶器の上絵付けの技法の一つです。 陶器の絵付けには、上絵のほかに下絵、イングレーズがありますが、上絵が最も焼成温度が低いため、鮮やかな色彩を表現することができます。 その上絵の中でも、漆蒔は深みのある艶やかな色が出る技法です。 漆蒔は、花を描くというものには適しておらず、一定の面積に均一に絵の具を乗せる技法です。そのため、幾何学的な模様が適していて、陶器の白地に深みのある色彩の線や図形のデザインが、とても美しく映えます。 この徳田さんのカップは、漆蒔の良さが最もよく表現されているものです。 さらに、漆蒔の青と銀彩のバランスがとてもきれいで、どことなくレトロな雰囲気も魅力です。 漆蒔という技法は、徳田さんの器以外では、ほとんど見かけることはありません。 大倉陶園という有名な食器メーカーが漆蒔の食器をつくっていますが、高価で、数も限られています。 漆蒔の深い色彩を、一度見てほしいです。 〈漆蒔の工程〉 ・上絵付されていない白い陶器の表面に、デザインに合わせて、テレピンでうすめた「漆」をぬります。 ・漆をある程度乾かしてから、上から粉の絵具をまぶします。漆が「のり」となって、絵の具を定着させます。 ・そのあと、800度前後で焼成すると、漆は燃えてなくなり、絵具だけが溶けて完成します。 徳田さんのこのカップの場合は、銀彩のために、もう一度、少し低い温度で焼成する必要があります。 ※ 電子レンジ、食洗器は避けてください。 漆蒔を継承する現代作家 徳田吉美 https://kinjonagoya.com/%e6%bc%86%e8%92%94%e3%82%92%e7%b6%99%e6%89%bf%e3%81%99%e3%82%8b%e7%8f%be%e4%bb%a3%e4%bd%9c%e5%ae%b6%e3%80%80%e5%be%b3%e7%94%b0%e5%90%89%e7%be%8e/
-

たべる たべる いのちを たべる わたなべちみえ
¥1,650
わたなべちみえさんの絵本です。ぼく(小出朝生)が編集しました。 愛知県の渥美半島の先端で、「どろんこ村」という農業・農家体験を実施している施設を運営しているのが、小笠原弘さんと渡辺千美江(わたなべちみえ)さんご夫妻です。 どろんこ村のホームページは https://www.doronkomura.com/ わたなべちみえさんは、「どろんこ村」を運営する中で、食べることの意味をずっと問い続けてきました。そして、気づいたことを、農家体験に参加する子どもたちへ伝えてきました。 この絵本は、そんな「食べること」の意味を、多くの子どもたちに伝えるために出版しました。 絵もすごくかわいいので、なんどでも繰り返し、眺めたくなる。そんな内容になっていると思います。 写真のオリジナルしおりをプレゼントします。 2022/8/25発行 B5判 28ページ 著者 わたなべちみえ 編集 小出朝生 出版社 : ブイツーソリューション
-

名古屋絵付け物語 陶磁器産業の勃興から衰退まで
¥2,200
ぼく(小出朝生)が、4年ほど前に執筆・編集した本です。 かつて名古屋市内で陶磁器製の食器に絵付けが施されて、たくさん海外に輸出していたことを知っている人は少ないと思います。 でも、昭和八~九年頃には日本の全輸出陶磁器の八〇%を名古屋で生産するようになり、開港以来、名古屋港から輸出される品目の輸出額一位は陶磁器で、昭和四十年代、自動車にトップの座を明け渡すまでほぼ一位を維持していました。 今は名古屋といえば自動車産業になっていますが、自動車の前は、繊維と陶磁器が名古屋という街の発展を支えていたんです。 そんな忘れ去れた名古屋の陶磁器絵付け産業の歴史をまとめた本です。 たぶん、読んでいただけるとわかると思いますが、名古屋在住の方でも知らないことばかりだと思います。 読んでもらえるとうれしいです。 写真のオリジナルしおりをプレゼントします。 2020/6/15発行 編集 小出朝生 発行 財団法人名古屋陶磁器会館 販売 風媒社 A5判 275ページ
-

手の仕事の旅 名古屋 誰かが、どこかで、なにかをつくっている
¥1,650
ぼく(小出朝生)が編集発行していた季刊雑誌「手の仕事」で取材した、名古屋周辺でものをつくっている人たちから数人を選んで、新たにもう一度お話を聞きに行ってまとめた本です。 写真は、友人のカメラマンの筒井誠己さんが撮っています。発行は2,015年だから、もう9年前になるんですね。内容は次のような感じです。 日本一の親子でつくる綿ふとん・丹羽ふとん店 頑固なチームがつくる夢の帽子・森安 年間限定六百本こだわりのランドセル・ナガエ 五十代目の木地師がつくるお盆・大蔵製盆 頭にぴったり合うかつらをつくる・京屋かつら 海の近くのハサミメーカー・忠圀鋏製作所 心を込めて鋼を打つ・兼由丸農具製作所 日本で唯一 ゼンマイ式置時計メーカー・ナルセ時計 チェンバロに恋して・クラヴサン工房アダチ 魔法の杖を追い求める・杉藤楽弓社 これまでも、これからも バイオリンをつくり続ける・鈴木バイオリン製造 手で曲げ、手で編む・大原製作所 明治十三年創業、今も新しい七宝に挑む・安藤七宝店 古い機械と家族でつくる溜醤油・帝国醸造 堀川の近くで檜の神棚をつくる・横井神具店 このうち、京屋かつらの京谷武弘さんはお亡くなりになってしまいした。今は息子の祐輝さんが後を継いでいます。ナルセ時計の成瀬さんは、今はもう時計はつくっておらず、老人介護事業 株式会社ちくたく亭のオーナーになっています。いろいろ変化はありますが、みなさん、今も、どこかでなにかをつくっています。 「仕事は人のためにするもの」。そんな大切なことを教えてくれた方たちの話をまとめた本をです。読んでもらえると、うれしいです。 写真のオリジナルしおりをプレゼントします。 A5判、155ページ 2015/2/18発行 編集・発行:手の仕事社 販売 : 風媒社
-

リュトン杯(ペガサス) 梅本尋司
¥11,000
リュトンとは、古代のペルシアからギリシアを含むバルカン半島一帯にかけてで用いられていたうつわで、それの梅本さん流に解釈したのがこの作品です。 高さ約4センチ 胚の直径約4センチ リュトンは、ワインなどを飲むのに使われたほか、宗教的な儀式にも使われたようです。鹿・山猫・羊・山羊などの動物の頭部を模した形の杯で、古代の人々は、リュトンを通った酒、ワインなどは神聖な力が宿ると信じられていたといわれています。 この作品は、もちろんうつわとして使用できるので、飲むなら、、、日本酒ですかね、、 もちろん、それは人それぞれですけど、、 ※なお、この作品は注文をいただいてから制作します。そのため、少しお時間をいただくことになります。また、まったく同じ作品とはならないことをご了承ください。 注文時にご希望があればお伝えください。 器をつくって名古屋で暮らす https://kinjonagoya.com/umemoto-izumida-pottery/
-

ラテ碗(鳥) 梅本尋司
¥11,000
ラテ碗(鳥) 高さ約7センチ 直径約13センチ 弥生時代に集落や田んぼ、井戸、お墓など、村の入口や異界との境界に飾られていた鳥形木製品。その鳥形木製品をイメージしたラテアート用の椀です。 日本において鳥の信仰は古く、『日本書紀』や『古事記』などに登場するほか、鳥の絵画が弥生時代の土器や銅鐸、古墳時代の装飾古墳 や埴輪に描かれています。古代人は、鳥への信仰を持っていたようですね。それは空を自由に飛ぶ鳥への畏敬の念があったのかもしれません。 梅本さんは、そんな古代の鳥への信仰の気持ちを、独自の釉薬によって表現しています。 もちろん、ラテ碗として使用できるので、ラテや珈琲、お茶を普通に飲むことができますし、ラテアートを楽しむこともできます。 ※なお、この作品は注文をいただいてから制作します。そのため、少しお時間をいただくことになります。また、まったく同じ作品とはならないことをご了承ください。 注文時にご希望があればお伝えください。 器をつくって名古屋で暮らす https://kinjonagoya.com/umemoto-izumida-pottery/
-

ブリコラージュマグ(縄文ー弥生) 梅本尋司
¥17,600
ブリコラージュとは「寄せ集めて自分でつくる」という意味。 このうつわは、作家の梅本さんの中で縄文と弥生のうつわのイメージを合わせて、つくったマグカップということですね。 高さ約12センチ 直径約10センチ 梅本さん独自の釉薬によって、縄文土器と弥生土器を融合させたイメージを表現しているのが特長。土は瀬戸のものです。 民俗学に興味を持ち、そこからイメージされる色や形、風合いを追及している梅本さんは、何度も釉薬のテスト繰り返しながら、自身が求めるイメージへと近づけていったようです。 このカップは、現代の空間に置くと、なにか異様な存在感を放つのがわかります。 もちろん、マグカップとして使用できるので、これで珈琲を飲むと、古代へと空想が広がっていくかもしれませんね。 ※なお、この作品は注文をいただいてから制作します。そのため、少しお時間をいただくことになります。また、まったく同じ作品とはならないことをご了承ください。 注文時にご希望があればお伝えください。 器をつくって名古屋で暮らす https://kinjonagoya.com/umemoto-izumida-pottery/
-

黒猫のカップ 泉田知香
¥4,950
黒猫のカップ 高さ約7センチ 直径約10センチ 泉田知香さんのかわいい黒猫のカップ。 カップの側面にも黒猫やパンダなどが描かれています。 カップのふちに黒猫がつかまっている姿がたまらないですね。 素材は半磁器で透明釉がかけられています。 お茶やコーヒーを楽しむのに最適なサイズで、手に持ちやすい形状で、 猫好きな方にもプレゼントにもおすすめですね。 電子レンジにも対応できます。 ※なお、この作品は注文をいただいてから制作します。そのため、少しお時間をいただくことになります。また、まったく同じ作品とはならないことをご了承ください。 注文時にご希望があればお伝えください。 器をつくって名古屋で暮らす https://kinjonagoya.com/umemoto-izumida-pottery/
-

バードカービング ルリビタキ 安藤公一
¥11,000
バードカービング作家として活動を続けている安藤公一さんのルリビタキの彫刻作品です。リアリティを追求したバードカービングというよりは、どこか懐かしい温もりを感じさせてくれるアート作品です。 このバードカービングは、飾るだけでなく、持つことでその美しさをいつも身近に感じられます。癒やしと美しさを取り入れたい、そんな方におすすめです。 高さ約15cm(鳥はほぼ実物大です) 素材 バルサ
-

ハードカービング ベニヒワ 安藤公一
¥11,000
バードカービング作家として活動を続けている安藤公一さんのベニヒワの彫刻作品です。リアリティを追求したバードカービングというよりは、どこか懐かしい温もりを感じさせてくれるアート作品です。 このバードカービングは、飾るだけでなく、持つことでその美しさをいつも身近に感じられます。癒やしと美しさを取り入れたい、そんな方におすすめです。 高さ約15cm(鳥はほぼ実物大です) 素材 バルサ
-

バードカービング シマエナガ 安藤公一
¥11,000
バードカービング作家として活動を続けている安藤公一さんのシマエナガの彫刻作品です。リアリティを追求したバードカービングというよりは、どこか懐かしい温もりを感じさせてくれるアート作品です。 このバードカービングは、飾るだけでなく、持つことでその美しさをいつも身近に感じられます。癒やしと美しさを取り入れたい、そんな方におすすめです。 高さ約15cm(鳥はほぼ実物大です) 素材 バルサ
-

まねき猫ペア 安藤栄子
¥9,600
元・鳴海製陶のデザイナーである安藤栄子さんが上絵付をしたまねき猫のペアです。 手のひらサイズの磁器製で、どんな部屋にもマッチする癒しアイテムです。 縁起のいいまねき猫があなたの日常に幸運を招いてくれるかもしれませんね。 心を温かくしてくれるまねき猫に、癒されてください。 左手を挙げているのが「人を招く」で、お店や会社へお客様を読んでくれるほか、恋愛や結婚も呼び寄せてくれると言われています。 右手を挙げているのが「福を招く」で、金運を上昇させてくれると言われています。 海外ではラッキーキャットとかウエルカムキャットと呼ばれて、徐々に人気が出てきているそうです。 高さは約9cm 幅は約5cm 奥行きは約5.5cm 食器大好き人間の食器デザイン https://kinjonagoya.com/%e9%a3%9f%e5%99%a8%e5%a4%a7%e5%a5%bd%e3%81%8d%e4%ba%ba%e9%96%93%e3%81%ae%e9%a3%9f%e5%99%a8%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3/
-

まねき猫ペア 安藤栄子
¥9,600
元・鳴海製陶のデザイナーである安藤栄子さんが上絵付をしたまねき猫のペアです。 手のひらサイズの磁器製で、どんな部屋にもマッチする癒しアイテムです。 縁起のいいまねき猫があなたの日常に幸運を招いてくれるかもしれませんね。 心を温かくしてくれるまねき猫に、癒されてください。 左手を挙げているのが「人を招く」で、お店や会社へお客様を読んでくれるほか、恋愛や結婚も呼び寄せてくれると言われています。 右手を挙げているのが「福を招く」で、金運を上昇させてくれると言われています。 海外ではラッキーキャットとかウエルカムキャットと呼ばれて、徐々に人気が出てきているそうです。 高さは約9cm 幅は約5cm 奥行きは約5.5cm 食器大好き人間の食器デザイン https://kinjonagoya.com/%e9%a3%9f%e5%99%a8%e5%a4%a7%e5%a5%bd%e3%81%8d%e4%ba%ba%e9%96%93%e3%81%ae%e9%a3%9f%e5%99%a8%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3/
-

まねき猫ペア 安藤栄子
¥9,600
元・鳴海製陶のデザイナーである安藤栄子さんが上絵付をしたまねき猫のペアです。 手のひらサイズの磁器製で、どんな部屋にもマッチする癒しアイテムです。 縁起のいいまねき猫があなたの日常に幸運を招いてくれるかもしれませんね。 心を温かくしてくれるまねき猫に、癒されてください。 左手を挙げているのが「人を招く」で、お店や会社へお客様を読んでくれるほか、恋愛や結婚も呼び寄せてくれると言われています。 右手を挙げているのが「福を招く」で、金運を上昇させてくれると言われています。 海外ではラッキーキャットとかウエルカムキャットと呼ばれて、徐々に人気が出てきているそうです。 高さは約9cm 幅は約5cm 奥行きは約5.5cm 食器大好き人間の食器デザイン https://kinjonagoya.com/%e9%a3%9f%e5%99%a8%e5%a4%a7%e5%a5%bd%e3%81%8d%e4%ba%ba%e9%96%93%e3%81%ae%e9%a3%9f%e5%99%a8%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3/